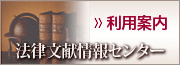所長メッセージ
(最終更新日:2014年9月21日)
比較法研究所にようこそ
所長 菊池 馨実

早稲田大学比較法研究所は、1958年、日本及び諸外国の法制度の比較研究を行い、日本の法学研究及び法学教育に貢献することを目的として設立されました。設立以来今日に至るまで、各国の法制度に関する資料の体系的な収集整備に努め、法令、判例及び法律関係雑誌の蓄積は、日本国内屈指の規模を誇っています。設立当初、欧米各国を中心とする法制度の研究を中心に行ってきた比較法研究所の活動は、日本の経済社会の発展と、日本固有の法制度の展開に伴い、次第に欧米各国やアジア諸国への日本の法制度の発信にも重きを置くに至っています。
比較法研究所には、127名の兼任研究員がおり、いずれも早稲田大学の専任教員で構成されています。また学外の研究者を招聘研究員として招いており、その数は82名に及びます。さらに、中国社会科学院法学研究所、精華大学法学院、メルボルン大学比較法国際法研究所、デューク大学ロースクール、マックス・プランク外国・国際刑法研究所、韓国法制研究院、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)と箇所間協定を締結し、交換研究員を受け入れています。その他にも、早稲田大学国際部国際課などを通じて、訪問学者、外国人研究員等を受け入れています。
比較法研究所では、現在18件の共同研究プロジェクトが行われ、兼任研究員及び招聘研究員による活発な比較法研究が行われています。また月に2回程度の頻度で、各法分野の最先端で活躍する全世界の法学研究者を招いて公開講演会を開催しています。これらの研究成果は、『比較法学』『比較法研究所叢書』として定期的に刊行されています。さらに日本の法制度と法律学の海外への発信を目的として、英文による「Waseda Bulletin of Comparative Law」を毎年発行しているほか、最近では、WEBサイトを利用した英文情報発信事業に力を入れており、最新立法・重要判例の紹介や学界の最新動向などを、学界の第一線で研究活動を行っている研究員が執筆し、随時掲載しています。
こうした研究活動のほか、2014年より、比較法研究所全体の研究プロジェクトとして、「持続可能社会への転換期における法と法律学の役割〜アジア・リージョナル法を展望して」というタイトルの共同研究を行っています。この研究は、絶え間ざる経済成長を不可欠の前提として発展を遂げてきた現代国家が、自然資源の枯渇を早め、生産と労働の過剰を帰結した反省に立ち、将来世代も視野に入れた持続可能社会への転換を図り、経済・社会・環境の三つの要素のバランスを取りつつ調整するための法と法律学の役割を考察しようとする取組みです。こうした研究は、自然環境問題にみられるように、日本国内はもちろんのこと、国民国家を超えたレベルでも切実に求められているといえましょう。そのモデルケースとして、EUという実験に学びながら、アジアの領域でのリージョナル法の展開を構想しています。このプロジェクトは、前・比較法研究所所長である楜沢能生教授(現・早稲田大学法学学術院長)の構想によるものであり、それを受け継いで引き続き展開するものです。
こうした様々な研究活動を通じて、比較法研究所は、世界各国の法学研究者と日本の法学及び法学研究者を結びつける「窓」として、積極的に貢献していきたいと念願しています。比較法研究所に対する皆様の積極的なアプローチを歓迎いたします。